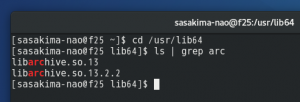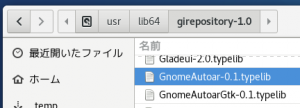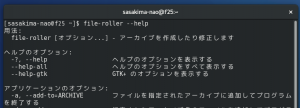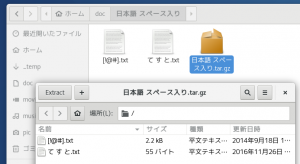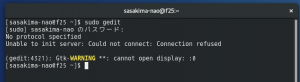先日 gnome-autoar というのを見つけた。
けれどソースコードには肝心の圧縮展開を行うコードは無かった。
GitHub – GNOME/gnome-autoar: Automatic archives creating and extracting library
中身をよく見ると archive.h を include している。
どうやら圧縮展開は libarchive 依存のミドルウエアってことみたい。
てゆーか libarchive って今は 7z 圧縮に対応しているってことかYO!
でも CB7 を作っても Nautilus 上でサムネイルされない。
おいおいマジで圧縮展開だけなのかよ。
いや、コミックブックアーカイブって五種類もあったのね。
ACE なんて見たことが無いし TAR はコレだけだと非圧縮だし無視でいいと思うが。
Comic book archive – Wikipedia
Evince でも CBR, CBZ, CB7 の三つをサポートしているみたい。
だけど Evince はどうやら p7zip 依存のようだ。
それに 7z だと file-roller で開くことができない、こいつも同様か。
ということで、現状では p7zip を入れておかないと色々不便だ。
sudo dnf install p7zip
United RPMS は unrar はあるけど rar は無いことに今頃気が付く。
コイツは削除して RARLAB のを自分で入れる。
よし3形式ともサムネイルとプレビューができるようになったぞ。
Evince, file-roller も対応、後は我がアプリ。
CBR と同じ方法でイケた、つーことで更新。
結局 gnome-autoar はどうでもよかった。
サムネイル表示されないのではビューアを作っても虚しいもんね。