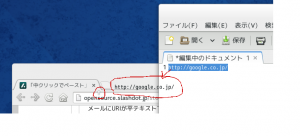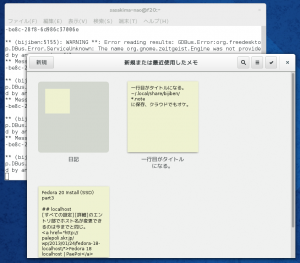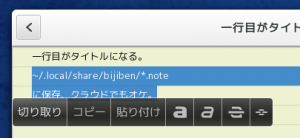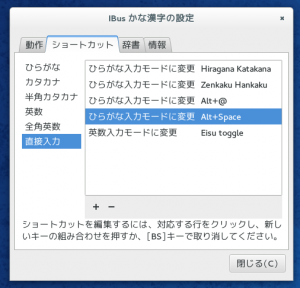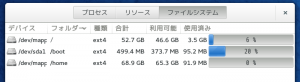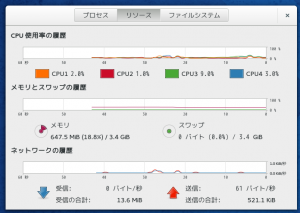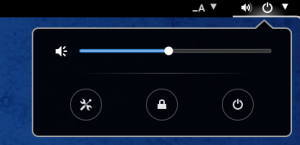Fedora 20 が出たので 19 から更新。
AMD Phenom II X4 955, AMD 880G, 4G Memory
というマシン構成は変わっていない、特に不満もないしもったいないし。
しかしこれではそろそろツマラン。
ということで今回は HDD から SSD に変更して導入してみた。
とりあえず評判の好いコレを購入。
128GB って今となってはさみしい容量だけど実は充分だよね。
3.5 インチベイに固定できる金具も付属で嬉しい。
Fedora Project ホームページ
ISO を DVD-R に焼いて SSD に取り替えとっととインストール。
インストール画面は以前と同じ、全部おまかせであっさり終る。
やはり修了で DVD-R は出てこない、USB メモリでやれってことかな。
イザ起動、即イジェクトボタンで DVD-R は出せる。
SSD 起動はやはり爆速、カーネル選択画面からたった十秒でユーザー選択に。
インストール直後のリソースはこの程度、128GB で問題なさそう。
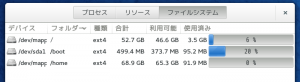
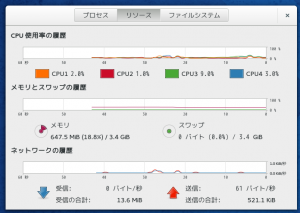
おまかせインストールでは SSD に最適という Btrfs にはならなかったか。
ext4 で充分速いから別にいいやという感じ。
さてデフォルト状態を色々確認してみる。
基本的に 18, 19 時と変わらない、デスクトップに物が置けないとか。
細かいことはサイドバーから過去記事で。
以下気が付いたこと。
システム関連のウインドウはことごとくタイトルバーが無くなっているぞと。
右上ユーザー名だったところが電源アイコンに変わった。
Alt を押すと電源アイコンがポーズアイコンに変わりサスペンドにできる。
ずっと GNOME を使っている筆者みたいな人ならすぐ解るけど、うーん。
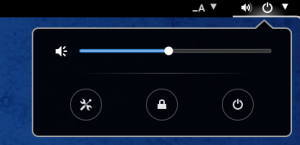
通知領域のニョッキが少々敏感になっていてウザい。
19 でウザさがなくなったのに戻したのだろうか?
なんか Super+A でのアプリが少ないな。
Boxes が無くなった、まあ設定項目が少なすぎでイマイチだったし。
ARMを正式サポートした「Fedora 20」がリリース、Fedoraプロジェクト10周年記念 | SourceForge.JP Magazine
qemu-kvm は virt-manager にしろということかな。
しかし日本の記事は絶対に Python をガン無視、かつ Rails の宣伝をするよな。
virt-manager は Python 製だということを知らないのだろうか?
Python は 2.7.5 と 3.3.2 がデフォルトで入っています。
seed, Gjs もあります、全然普及しないけど。
他にも何か無くなっているいる気がするけど、後で確認しよう。
手動アップデート確認は[すべての設定][詳細]に戻ったようだ。
更新通知は Fedora 19 で完璧になったので気にしなくてもいいと思う。
アプリのインストールは[ソフトウエア]で行うようになった。
上部の時計が変だと思ったら等幅の VL Gothic になっている。
org.gnome.desktop.interface font-name は Cantarell 11 なのに。
他色々な場面でフォントに違和感、いや綺麗に表示されているんだけど。
VL P Gothic をインストールしようとしたけど出てこないのだが。
VL Gothic Font Family
上記から落として自分でインストールしたけど。
org.gnome.desktop.interface toolbar-style も適用されない。
デフォルトアプリでツールバーが残っているのは Gedit だけだとはいえ何故だ?
ibus-kkc は Fedora 19 ではイマイチだったけど悪くない。
バージョンは上がっていないので ibus 側が安定したのだろうと予想。
変になったら ~/.config/ibus-kkc 以下を削除すればいいはず。
ギョッとする変更や致命的なバグは何も無いみたい。
通知領域のニョッキが気になるくらいで普通に使える。
週末に必要アプリの導入でもしますか、今日はもう寝る。
しかし SSD は最高、変更して正解。
アプリの起動をほとんど待たなくていいのは本当に素晴らしい。