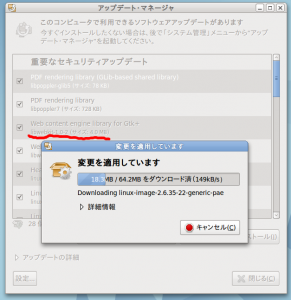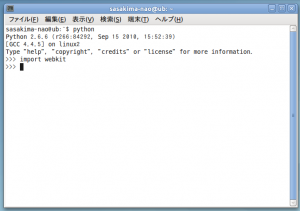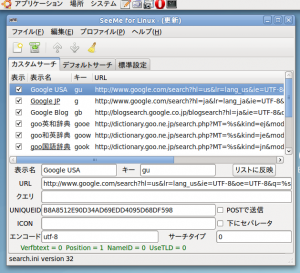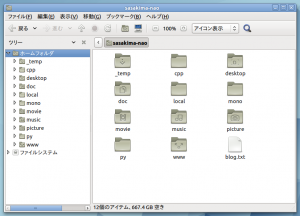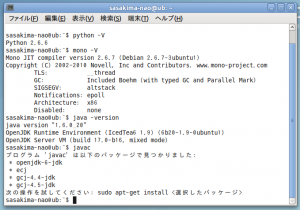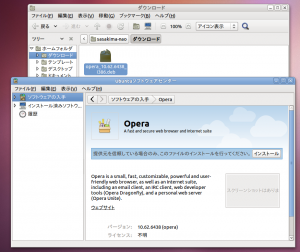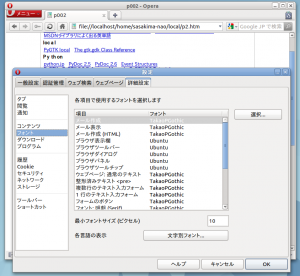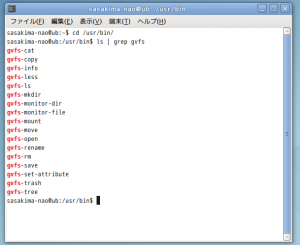Ubuntu 10.10 のアップデート、61MB もあるんかい!
ってよく見たら libwebkit なんてのがあるんだけど…
WebKit な Epiphany は GNOME 標準だけど Ubuntu では除かれているのに。
ライブラリだけは存在しますということなのかな?
まてよ、そういうことならデフォルト状態で Python から使えるかも。
>>>import webkit
10.10 はデフォルトで利用できるようです、てゆーか
/usr/share/doc/python-webkit/examples/browser.py
にサンプルコードがあるわな。
このサンプルコードを試してもいいけど最小限のコードを書いてみる。
#!/usr/bin/env python
#-*- coding:utf-8 -*-
import gtk
import webkit
class WebKitTest(gtk.Window):
"""
WebKit test for Python
from Ubuntu 10.10
"""
def __init__(self):
# Window
gtk.Window.__init__(self)
self.connect("delete-event", gtk.main_quit)
self.resize(640, 480)
# WebKit
w = webkit.WebView()
w.load_uri("http://google.co.jp/")
# ScrollWindow
sw = gtk.ScrolledWindow()
sw.set_policy(gtk.POLICY_AUTOMATIC, gtk.POLICY_AUTOMATIC)
# add
sw.add(w)
self.add(sw)
self.show_all()
if __name__ == "__main__":
w = WebKitTest()
gtk.main()
おぉ、コレだけで使えるのか。
GtkScrolledWindow を噛まさないと縦長のページで悲惨になるので注意ね。
後はサンプルコードを見ながらチマチマ弄くれば立派な自作ブラウザになりそう。
とにかく Python だけで何でも作れてしまう。
デフォルト状態でも作って遊べるというのはやはり素晴らしい。
Windows ではこんなこと考えられないものなぁ。