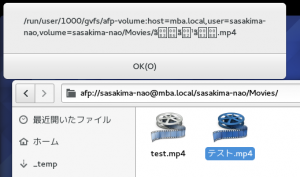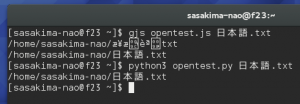前々回の記事で Gjs 3.18 の ARGV は日本語未対応だと解った。
一応、Gjs は GTK+ 等と同様 GNOME の一部なのでバージョンは GNOME と同じ。
今後変わるかもしれないけど現状では各自で対策しなければ。
ただし単純に変換すればいいわけではない。
昔と違って今はパラメータが URI である場合もあるのだ。
それを吸収するため GtkApplication が作られたのかも。
function messagebox(text) {
let dlg = new Gtk.MessageDialog({
transient_for: null,
modal: true,
type: Gtk.MessageType.WARNING,
buttons: Gtk.ButtonsType.OK,
text: text
});
dlg.run();
dlg.destroy();
};
ARGV.forEach(function(element) {
messagebox(element);
});
とりあえずこんな処理を入れて実験。
Mac に日本語ファイル名の動画を置いて Fedora からダブルクリック。
ダブルクリックだとマウント先が渡るのね。
そして日本語は見事に化けるという。
afp の URI で渡しても再生できる、http もいける。
そもそも URI の場合日本語等は既にエンコードされているはず。
ならばこうすればいいんでないの。
const Y901Application = new Lang.Class({
Name: 'Y901Application',
Extends: Gtk.Application,
_init: function() {
this.parent({
flags: Gio.ApplicationFlags.HANDLES_OPEN
});
},
vfunc_open: function(files, hint) {
let uri = files[0].get_uri();
let w = new Y901Window(this);
w.set_uri(uri);
},
vfunc_activate: function() {
new Y901Window(this);
}
});
let argv = [System.programInvocationName];
ARGV.forEach(function(element) {
if (element.indexOf("//") == -1) {
argv.push(decodeURIComponent(escape(element)));
} else {
argv.push(element);
}
});
let application = new Y901Application();
application.run(argv)
“//” があれば URI 確定なのでそのまんま。
パス名なら日本語ファイル名かもしれないから変換処理。
で argv を作り直して g_application_run の引数にする。
これで現状何も問題なく使えている。
てゆーか、ARGV の仕様をなんとかしてくれないかなぁ。